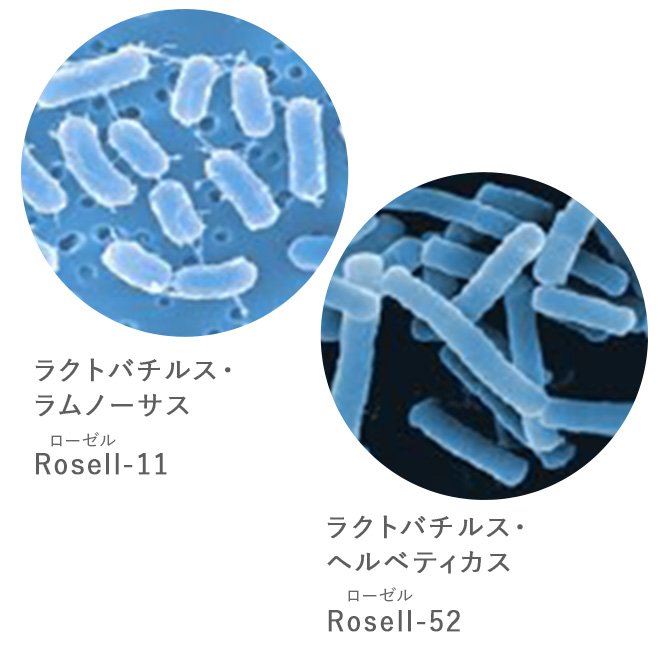早産とは
日本では妊娠22週0日~36週6日までの分娩を「早産」といいます。早産とは、胎児の発育がまだ不十分であるにも関わらず、早期に陣痛や子宮頸管熟化(頸管の軟化や開大)、破水が生じることによって、予定日よりも早く生まれてしまうことをいいます。早産児は死亡率も高く、救命されても後遺症や合併症を引き起こす可能性が高いです(※1)。

早産は自然早産と人工早産に分けられます。自然早産は様々な原因により、妊娠の継続が不可能となり自然に分娩に至ることをいいます。人工早産は母児の救命のために人為的に出産させることをいいます。それぞれの頻度は自然早産が75%、人工早産が25%です(※1)。
自然早産の主な原因として、前回の妊娠が早産であった、過去に子宮頸管無力症の診断を受けたことがある、子宮頸部の手術を受けたことがある等があげられております。また現在、細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎(じゅうもうまくようまくえん)、子宮頸管無力症、多胎妊娠、羊水過多症にかかっていることや、やせている、喫煙の習慣やストレスがあるなどもあげられております(※1)。
我が国の早産率は増加傾向にあり、年間約6万の早産数があります。特に予後が悪い28週未満となる早産の割合はこの30年ほどの間で2倍以上に増加しています(※1)。早産増加は、「晩婚による高齢出産などの年齢的な要因」、「体外受精による多胎妊娠などの理由で行われた医療行為」、「喫煙や過激なダイエットによる環境要因」、「細菌性膣症や性感染症の増加等の感染症」の各要因が関与しているとされております(※1)。
日本でおこなわれた研究での結果によると、以前に早産を経験したことのある妊婦が再び早産となる割合が16.3%、数多く早産を経験した方は早産となる危険率が2.26倍高いとの報告があります(※2)。このように、早産は一度起きてしまうと繰り返すことが多いので、早産になるリスクをできるだけ回避できる日常生活を過ごせるように心がけましょう。
低出生体重児とは
「低出生体重児」とは出生体重が2500g未満の赤ちゃんをいいます。さらに、出生体重が1500g未満の赤ちゃんは「極低出生体重児」、1000g未満の赤ちゃんは「超低出生体重児」と呼ばれております(※3)。

低出生体重児の割合は男女ともに増加傾向でしたが、近年は歯止めがかかり横ばい状態となっており、低出生体重児であった割合は男児で8%程度、女児で11%程度でした(※4)。
低出生体重児が生まれる母体側の原因として、高血圧、妊娠前の糖尿病、腎疾患、甲状腺疾患、自己免疫疾患、抗リン脂質抗体症候群、チアノーゼ型心疾患などの合併症が、喫煙やアルコールなどの生活習慣が、その他低身長、出生時低体重、LGA児分娩既往、妊娠前のやせ、体重増加不良などが示唆されております(※5)。一方、生まれてきた胎児側においても、運動障害や知的障害などの発達障害を起こす可能性があります(※3)。
早産と細菌性膣症との関係
細菌性膣症は早産となることに深く関与しております。ガイドラインにおいても、細菌性膣症である妊婦は、早産のハイリスクと認識し管理することが必要とされております(※5)。
細菌性膣症と早産に関して、いくつかの研究が行われています。細菌性膣症、トリコモナス症、カンジダ症の治療を行うことで37週未満の早産率や、早産による2500g以下及び1500g以下の低出生体重児出生を有意に低下するとの調査結果があり(※6)、ガイドラインにおいて早産予防を目的とした細菌性膣症のスクリーニング調査を行う場合には、妊娠20週未満に実施することを考慮すべきとされております(※5)。
妊娠時に細菌性腟症であった妊婦は、全妊婦のおよそ18%という報告があります(※7)。決して少ない割合ではありません。ガイドラインでは、症状のある細菌性膣症になった場合、抗菌薬による治療が推奨されているように(※5)、早産とならないためにも細菌性膣症に対して何らかの治療が必要な場合もあります。

早産の原因で多いのは絨毛膜羊膜炎(じゅうもうまくようまくえん)
細菌性膣症だけでなく、絨毛膜羊膜炎も早産の大きな原因のひとつです。絨毛膜羊膜炎を発症すると短期間で早産に至ります。ガイドラインによると、妊娠32週未満で早産であった人の約50%に絨毛膜羊膜炎が認められることから、絨毛膜羊膜炎が早産の原因と考えられています(※5)。また、別の報告によると、早産であった人での絨毛膜羊膜炎の罹患率は34週時で16%であったのに比べて20~24週時で66%と、出産時の妊娠週数が早いほど絨毛膜羊膜炎の罹患率が高く、また25~29週時点での周産期胎児死亡率は明らかに高いとの結果でありました(※8)。このように、絨毛膜羊膜炎を罹患していると早産になりやすく、同様に低出生体重児を出生する原因にもなりやすいです。
絨毛膜羊膜炎である妊婦は、全妊婦のおよそ2%弱と推定されます。これは、37週未満での早産率が約5~6%との報告(※1)および37週未満の早産全体での絨毛膜羊膜炎の罹患率が31%との報告(※8)から推定しております。
絨毛膜羊膜炎は、細菌性膣症の原因菌の一部が子宮頸管へ、さらにその一部が絨毛膜羊膜へと上行性に感染し、胎児付属物の卵膜(絨毛膜、羊膜)に感染して生じる炎症性疾患をいいます(※1)。
絨毛膜羊膜炎は、膣分泌液、子宮頸管粘液より乳酸菌の減少や炎症マーカーにより行われ、組織学的(不顕性の)絨毛膜羊膜炎と診断されます(※1)。さらに、自覚的に発熱(38℃以上)が認められ、かつ母体の頻脈(脈拍数が100bpm以上)、子宮の圧痛、膣分泌物・羊水の悪臭、白血球増多(白血球数が15,000/μL以上)の4項目のうち1項目以上がある場合に、臨床的(顕在性の)絨毛膜羊膜炎と診断されます(※5)。
臨床的絨毛膜羊膜炎と診断された場合、母体や胎児に及ぼす影響を考慮して、ガイドラインによると、妊娠26週以上であれば、陣痛発来を待機せずに24時間以内の分娩を目指した分娩誘発もしくは帝王切開を行うことを考慮すべきとされています(※5)。このように、絨毛膜羊膜炎を発症すると、早産や死産などに至るリスクが大きくなるため、絨毛膜羊膜炎にまで至らない段階である細菌性膣症にかからないように予防に努めるか、細菌性膣症の段階で治療されることが大事です。
膣内フローラの改善を

早産となってしまう原因として、細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎(じゅうもうまくようまくえん)があります。妊娠した時点で検査をおこない、細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎であると判明した場合には、原因は(悪玉)菌やカンジダ菌などであるため、抗菌薬を用いて治療しますが、治療に際しては、胎仔への影響を考えて妊娠前に比べて制限されますし、抗菌薬を用いて治療したとしても必ずしも治るとは限りません。このため、細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎とならないことが大切です。
細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎が起きる発端は、膣内フローラの乱れから始まります。すなわち、これから妊娠を希望される方にとって、膣内フローラを正常な状態にすることが大切になってきます。
さらに、細菌性膣症や絨毛膜羊膜炎の治療に際して抗菌薬を用いることがありますが、抗菌薬を用いることで、場合によっては、膣内フローラがさらに乱れてしまうこともあります。
海外において、帝王切開後の抗菌薬投与によって乱れた膣内フローラが、乳酸菌の一種であるRosell-11&52を摂取することで正常となったとの報告があり(※9)、乳酸菌サプリメント摂取によって乱れた膣内フローラを正常な状態に戻すことが期待できます。
今後、妊娠の可能性のある方におかれては、日頃から膣内ケアに心がけるようにしましょう。
※1 医療情報科学研究所/病気がみえる(産科) 2018 p162-167 p172-177 ※2 Yamashita M,et al. : J Obstet Gynaecol Res. 2015. 41:1708-1714
※3 大阪府立母子保健総合医療センター企画調査部/低出生体重児保健指導マニュアル~小さく生まれた赤ちゃんの地域支援~ 2012 p3,p5-13
※4 厚生労働省/平成30年我が国の人口動態(平成28 年までの動向)2018 p13
※5 日本産科婦人科学会・日本産婦人科医会/産婦人科診療ガイドライン(産科編) 2017 p158-162,p177-181,p335-336
※6 Sangkomkamhang US, et al.: Cochrane Database Syst Rev. 2015. 2:Art No. CD006178
※7 Shimano S, et al.: J Obstet Gynaecol Res. 2004. 30:230-236
※8 Lahra MM, et al.: Am J Obstet Gynecol. 2004. 190:147-151
※9 Liskovich VV,et al.:Health. 2010. 1:63-66